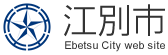低炭素建築物認定手続きについて
おしらせ
低炭素建築物認定の工事完了報告がオンラインでできるようになりました。
詳しくは、「7 工事完了報告 電子申請」をご確認ください。
1 低炭素建築物の認定について
低炭素建築物とは建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に役立てる措置が講じられている、市街化区域等内に建築される建築物をいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、この建築物の低炭素化のための計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(江別市長)に認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
制度関連情報
2 認定基準(市街化区域内における計画であり、下表1~3のすべてに適合すること)
| 1 | エネルギーの使用の効率性に関する基準(法第54条第1項第1号) | 外皮性能の基準に適合すること |
| 一次エネルギー消費量の基準に適合すること | ||
| その他措置の基準に適合すること(再生可能エネルギー源(太陽光、風力等)の利用に役立てる設備を設けること及び(節水対策や雨水・排水対策の導入など9つの項目のうち1つ以上に適合すること) | ||
| 2 | 基本方針(法第54条第1項第2号) | 「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」に従い、都市の緑地の保全に配慮すること |
| 3 | 資金計画(法第54条第1項第3号) | 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること |
※令和4年10月1日から認定基準、申請単位が変更となっています。詳細については認定基準等見直し概要(国土交通省作成資料) [PDFファイル/331KB]をご確認ください。
都市の緑地の保全配慮に関する基準
(1)都市計画法による地区計画(緑地保全に関する規定)
地区計画区域において、地区整備計画に緑地保全の規定が定められている場合は、これに適合する必要があります。
※現在緑地保全に関する規定が定められている地区計画:「元江別中央地区」地区計画
詳細は、江別市地区計画のページをご覧ください。
(2)建築基準法による建築協定(緑地保全に関する規定)
建築協定区域において、協定基準に緑地保全の規定が定められている場合は、その規定に適合する必要があります。
※現在緑地保全に関する規定が定められている建築協定はありません。
(3)都市緑地法による緑地協定
緑地協定区域においては、協定の規定に適合する必要があります。
(4)次に掲げる区域内に建築されるものでないこと
都市計画緑地(都市計画法第11条第1項第2号)
3 認定申請の流れ
| 必要に応じて地区計画等の届出 | 技術的審査 |
登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で、認定基準の「2基本方針」を除くすべての基準について審査を受け、適合証の交付を受けてください。 |
|
|---|---|---|---|
| → | ↓ | ||
| 認定申請 |
適合証及びその他必要書類を揃え申請してください。(申請先:江別市建設部建築指導課建築指導係) |
||
| ↓ | |||
|
認定通知 |
認定申請書受付から認定通知まで、1週間程度かかります。 | ||
| ↓ | ※認定申請後であれば、認定通知前であっても工事着手は可能です。 | ||
| 工事着工 |
|
||
| ↓ | 認定の内容に変更があった場合は、変更認定申請が必要です。 | ||
| 工事完了 |
工事完了報告をしてください。(提出先:江別市建設部建築指導課建築指導係) |
||
4 申請必要書類
1 法施行規則第41条に掲げる申請書及び添付図書
2 同条において、所管行政庁(江別市)が必要と認める図書(以下参照)
- 委任状(申請者が手続きを他者に委任する場合)
- 登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による「技術的審査適合証」
- その他
都市の緑地の保全配慮に関する基準への適合が確認できる書類(各届出の写し、協定運営委員会の承認を得た図面など)(※)
(※)地区計画区域または建築協定区域において緑地保全に関する規定が定められている区域、または、緑地協定が定められている区域における申請の場合に限ります。
※添付図面は、登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関の審査を受けた後のものを添付してください。
※提出部数 2部
5 登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関
認定申請を行う前に、以下の機関で認定基準の「2基本方針」を除くすべての基準について審査を受け、適合証の交付を受けてください。
・住宅の品質確保の促進に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関(住宅の技術審査が可能)
・建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(非住宅の技術審査が可能)
※江別市を業務区域に含めている上記機関は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HPから検索ができます。
6 申請手数料
低炭素建築物認定申請手数料一覧 [PDFファイル/188KB]
| 区分 | 単位 | 低炭素認定申請手数料(円) | 変更認定申請手数料(円) | |||||||
| 技術的審査を受けた場合 | 技術的審査を受けていない場合 | |||||||||
| 戸建て住宅、長屋、共同住宅、複合建築物の住宅部分 | 1戸 | 6,000 | 標準計算法 | 35,000 | 誘導仕様基準 | 19,000 | ※左記に掲げる額の2分の1の額 | |||
| 2戸以上5戸以内 | 11,000 | 69,000 | 34,000 | |||||||
| 6戸以上10戸以内 | 17,000 | 97,000 | 49,000 | |||||||
| 共同住宅の共用部 | 300平方メートル以内 | 11,000 | 108,000 | 49,000 | ||||||
| 300平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 28,000 | 178,000 | 83,000 | |||||||
| 非住宅または複合建築物の非住宅部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 11,000 | モデル建物法 | 11,000 | 標準入力法 | 239,000 | モデル建物法 | 93,000 | |
| 300平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 19,000 | 19,000 | 306,000 | 109,000 | ||||||
| 1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 28,000 | 27,000 | 379,000 | 149,000 | ||||||
| 2,000平方メートル超~5,000平方メートル以内 | 80,000 | 78,000 | 538,000 | 238,000 | ||||||
■評価機関審査とは(以下のいずれかの機関による技術的審査をいいます。)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
・建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
※性能評価機関審査には、改めて各機関が定める手数料がかかります。
7 工事完了報告
窓口申請
必要書類
- 工事完了報告書 [Wordファイル/37KB](要綱第3号様式)
- 工事監理報告書 [Wordファイル/47KB](建築士法第20条第3項)等、計画に基づき工事が行われたことが確認できる書類
【軽微な変更がある場合】
- 変更内容がわかる書類
電子申請
必要書類
電子申請を始める前に、下記書類をご準備ください。申請時にアップロードをする必要があります。
- 工事監理報告書 [Wordファイル/47KB](建築士法第20条第3項)等、計画に基づき工事が行われたことが確認できる書類
【軽微な変更がある場合】
- 変更内容がわかる書類
申請フォーム
下記を選択すると、Logoフォームの低炭素建築物認定工事完了報告フォーム画面に移動します。
※電子申請の場合、受付印を押した控えの返却は行っておりません。電子申請完了後に自動送付される送信完了メールをご活用ください。