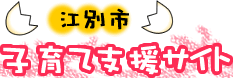児童手当
児童手当は、家庭などにおける生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに貢献することを目的として、児童を養育する方に支給される手当です。
【重要】令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当制度が改正されました。
【重要】現在、江別市で児童手当を受給しており多子加算(第3子以降加算)の適用を受けている方で、条件に該当する場合は令和7年4月以降も継続して多子加算の適用を受けるためには「児童手当額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
対象児童
高校生年代までの児童(18歳に達する年度の3月31日まで)
支給要件
対象児童を養育している方が受給できます。
父母に養育されていない児童については、児童を監護し、生計を維持する方が受給資格者となります。
※原則として児童の住所が日本国内にあることが必要です。
※児童が施設などに入所している場合は、原則として、入所している施設の設置者などが児童手当を受給することになります。
受給するには
児童手当を受給するには、子育て支援課(市役所本庁舎西棟2階)または市役所大麻出張所で手続きが必要です。
公務員については、勤務先で支給されますので、勤務先の給与事務担当者にお問い合わせください。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員でなくなったとき、施設を退所したときなど、新たに受給資格が生じた場合も同様です。
提出・お持ちいただくもの
・児童手当認定請求書 [PDFファイル/105KB]
・添付の必要な書類
1.3歳未満の児童を監護している場合、次のアかイのいずれかの写し
ア.請求者が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
イ.マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
2.通帳の写し等(請求者本人名義に限ります)
※金融機関の名称、支店名、口座番号、口座名義が記載されたもの
3.別居している児童を養育している場合
(1)別居監護申立書 [PDFファイル/31KB]
(2)児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※別居している児童の住所が江別市内の場合は不要です。
※この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
手当の額
| 児童の区分 | 支給額/月 |
|---|---|
|
3歳未満の児童(第1子、第2子) |
15,000円 |
| 3歳未満の児童(第3子以降) | 30,000円 |
| 3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第1子、第2子) | 10,000円 |
| 3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第3子以降) | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
所得上限限度額以上となったために受給資格がなくなった方へ
児童手当が支給されなくなった後に、以下1、2のように児童手当等を受給できる範囲の所得となった場合には、あらためて認定請求書等の提出が必要となります。
1.令和6年度(令和5年分)の所得が上限限度額未満となったとき
令和6年5月中もしくは、令和6年度「市民税・道民税税額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請いただいた場合は、令和6年6月分から支給されます。
2.所得の更正等により、令和4年度(令和3年分)もしくは令和5年度(令和4年分)の所得が上限限度額未満となったとき
更正等の後に届いた令和4年度もしくは令和5年度の「市民税・道民税税額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請いただいた場合、令和4年6月分もしくは令和5年6月分から支給されます。
※申請が遅れた場合は、申請月の翌月分からの支給となり、支給できない月が発生しますのでご注意ください。
支給日
原則、支給日は各月の9日です。支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日に支給します。
| 支給月 | 対象の手当 | 支給予定日 |
| 2月 | 12月分から1月分まで | 2月9日 |
| 4月 | 2月分から3月分まで | 4月9日 |
| 6月 | 4月分から5月分まで | 6月9日 |
| 8月 | 6月分から7月分まで | 8月9日 |
| 10月 | 8月分から9月分まで | 10月9日 |
| 12月 | 10月分から11月分まで | 12月9日 |
その他の手続き(主なもの)
| 提出を必要とするとき | 届出の種類 ※必要書類 |
|---|---|
| ・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき ・施設入所や里親委託により支給対象となる児童が減ったとき(養育児童が0人の場合は消滅届) ・施設退所や里親解除により支給対象となる児童が増えたとき |
|
| ・離婚により支給対象の児童を養育しなくなったとき ・施設入所や里親委託により児童を養育しなくなったとき ・受給者が公務員となったとき |
受給事由消滅届 [PDFファイル/106KB] |
| ・振込先の口座を変更したいとき |
金融機関変更届 [PDFファイル/45KB] ※児童手当の振込先として公金受取口座を指定した後、マイナポータル上で公金受取口座を変更した場合でも、市への金融機関変更届の提出が必要です。詳細については下記PDFファイルをご覧ください。 |
| ・別居した児童を引き続き養育すると |
別居監護申立書 [PDFファイル/31KB] |
| ・受給者が亡くなられたとき | 未支払児童手当請求書 [PDFファイル/117KB] ※支給対象児童の預金通帳の写し(2名以上いる場合は代表者1名分) ・受給者の配偶者等、新たに子どもを養育することになった方は、新規の認定請求が必要です。 |
| ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(住所が他市町村の場合のみ) ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき ・受給者の加⼊する公的年⾦種別が変わったとき(児童が3歳未満の場合のみ) ・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき |
氏名及び住所等変更届 [PDFファイル/136KB] |
| ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる⽗⺟から「⽗⺟指定者」の指定を受けるとき | 父母指定者指定届 [PDFファイル/97KB] |
|
・子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある大学生年代(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)の子を監護している方 ※現在児童手当を受給している方、新規に児童手当を申請する方のどちらも、該当する場合は提出が必要です。 ※進学・就職等の状況に関わらず、また、留学中であっても「経済的負担」があれば算定されます。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/61KB] |
電子申請について
令和5年2月1日から、総務省が運営するマイナポータル内のぴったりサービスを利用することで、児童手当の一部手続きについて電子申請ができるようになりました。
手続きに必要なもの
ぴったりサービスのご利用に当たっては、下記のものが必要となります
1.マイナンバーカード
2.スマートフォンまたはパソコン+カードリーダー
※スマートフォンやカードリーダーは、マイナンバーカードの読み取りに対応したものが必要です。
ぴったりサービスを利用できる手続き
- 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当の額の改定の請求及び届出
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 児童手当の現況届
- 受給事由消滅の届出
- 未支払の児童手当の請求
- 児童手当に係る寄附の申出
- 児童手当に係る寄附変更等の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
電子申請手続きの詳細については、ぴったりサービスについて(外部リンク)をご確認ください。
申請フォームについては、ぴったりサービス 検索ページ(外部リンク)をご確認ください。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況をお知らせいただく届出ですが、国の制度改正に伴い、令和4年度からは、公簿などで受給者の状況を確認できる方については現況届の提出は原則不要となりました。
※ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。対象となる方には市から現況届を発送しておりますので、6月1日の状況を記載し、必ず提出してください。(状況に応じて現況届のほかに書類を提出していただく場合があります。)
この届の提出がないと、10月期以降(8月分~)の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
・前年度、現況届の提出を求められたが未提出の方
・配偶者からの暴⼒等により、住⺠票の住所地が江別市と異なる方
・支給要件児童の⼾籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法⼈である未成年後⾒⼈、施設等の受給者の方
・監護相当・生計費の負担についての確認書を提出しており、進学せず就職等する子を監護している方
・その他、江別市から提出の案内があった方
上記に該当する方で、現況届が届かない場合は、下記問い合わせ先に確認してください。
受付時間
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)