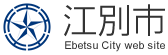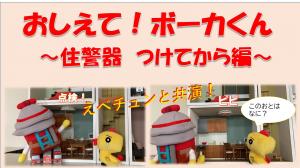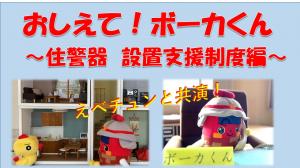住宅用火災警報器について
ご存じですか?すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要です。
住宅用火災警報器の設置及び維持の方法などは、国の基準に従い、江別市火災予防条例で定められています。
住宅火災における逃げ遅れによる死者を減少させることを目的として、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置義務があります。
住宅用火災警報器とは?
住宅用火災警報器とは、天井や壁の高所に取り付け、火災の煙や熱を感知し、居住者に警報音で火災の発生を知らせる機器です。
電気屋さんやホームセンター等で購入することができ、ドライバーなどで簡単に取り付けることができます。
住宅用火災警報器はどこに付けるの?
設置場所は、「寝室」、「台所」です。
そして、2階に寝室がある場合には、「階段」への設置が必要です。
詳しくはこちらの動画で!!
ボーカくんと住宅用火災警報器について学びましょう!
住宅用火災警報器の種類
住宅用火災警報器には、いろいろな種類があります。例えば、警報器の電源には、電池によって稼働する「電池タイプ」と一般電源を用いる「電源タイプ」があり、電池タイプは電池が少なくなると警報音で知らせてくれるので電池が切れる心配は少ないです。また、警報器の感知方法には、煙を検知する「煙式」と空気中の熱を検知する「熱式」があり、火災では最初に煙が発生することから煙式の方がより早く火災を検知することが可能です。
熱を感知する警報器

煙を感知する警報器



その他の警報器
火災になった部屋の感知器だけでなく、無線によって離れた部屋や別の階に設置されているすべての感知器を連動させて警報音を鳴らす「連動型住宅用火災警報器」などもあります。
点検や交換は必要なの?
住宅用火災警報器が正常に作動するか、定期的に点検してください。設置してから時間が経過するとセンサーの寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。1か月に1度は点検するようにしましょう。センサーが感知しなくなったり、電池が切れたりしたら、交換しましょう。
点検方法
本体についている「ヒモを引く」または「ボタンを押す」ことで、だれでも簡単に点検できます。
交換について
住宅用火災警報器を点検して、何も音が鳴らないなど電池切れや故障の場合はすぐに交換しましょう。
また、住宅用火災警報器には、見やすい位置に「自動試験機能付」または「交換期限」の表示があります。自動試験機能による故障警報が鳴った場合、または交換期限が経過した場合には、住宅用火災警報器を交換してください。
なお、交換の目安は10年です。
詳しくはこちらの動画で!!
ボーカくんが点検と交換について教えてくれます!
設置支援制度について
高齢者や身体が不自由な方など、自分で取り付けることが困難な方々は、設置支援制度をご活用ください。消防職員や消防団員がご自宅へ訪問し、警報器の取付けや交換を行います。
取付けや交換は無料で行いますが、住宅用火災警報器はご自身で用意してください。
詳しくは、消防本部予防課または最寄りの消防署出張所にご相談ください。相談は、電話でもお受けいたします。
| 江別消防 | 連絡先 |
|---|---|
| 消防本部予防課 | 011-382-5430 |
| 消防署江別出張所 | 011-382-2075 |
| 消防署野幌出張所 | 011-382-3444 |
| 消防署大麻出張所 | 011-382-8333 |
詳しくはこちらの動画で!!
設置支援制度を利用される方が増えていますので、ぜひご覧ください。
住宅用火災警報器の効果
住宅火災により死に至った原因の7割が「逃げ遅れ」ということから、早期に火災に気付くことができれば死者の減少を図ることができます。
江別市でも数多くの奏功事例があり、令和4年1月から9月までで6件の奏功事例が報告されています。奏功事例のページでは、出火に至った経緯なども書いてありますので、ぜひご覧ください。
住宅用火災警報器の設置状況等調査の結果(令和6年6月1日時点)
| 地域 |
設置率※1 |
条例適合率※2 |
|---|---|---|
|
日本全国(平均) |
84.5% | 66.2% |
|
北海道(平均) |
84.3% | 66.0% |
| 江別市 | 77.0% | 63.0% |
※1 全世帯(調査世帯)に対する設置世帯(一部設置含む)の割合。
※2 全世帯(調査世帯)に対する市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分すべてに設置されている世帯の割合。
江別市の設置率及び条例適合率は、全国と全道の平均を下回っていることから、適正な設置・維持管理に対する意識のさらなる向上が求められています。
住宅用火災警報器の悪質商法にご用心
悪質な訪問商法のひとつに「消火器の点検に来ました!」と事業所の窓口などで告げ、点検が終了した後に、高額な請求を行う事例があります。
これと同じ事例が住宅用火災警報器においても発生することが予想されます。「消防法が改正されたので、今すぐ住宅用火災警報器を設置しなければならない!」、「この火災警報器でなければならない!」などと言って火災警報器の購入を強引に迫る業者に対しては注意してください。
また、公的な機関や消防署を名乗って設置を勧める業者にも、注意が必要です。
訪問販売など、その場で契約を求められる場合は不用意に契約せず、不審に思われたときは、はっきり断ることが必要です。
- 「今だけです!」、「あなただけです!」などと契約を急がせる業者には要注意!
- 訪問販売業者と契約するときは、その場ですぐ契約するのではなく、よく考えて他の業者と見積もりを比較するなど十分検討しましょう。
その場ですぐ決めずに、必ず家族や友人に相談しましょう! - 悪質業者は、言葉巧みに勧誘してきたり、有無を言わさず契約させようとしてきます。安易にサインや押印を行わず、誰かに相談してください。
公的機関の職員が一般家庭を訪問し、火災警報器を販売することはありません!