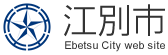退職所得の課税
退職所得に係る住民税の算出方法
退職所得に係る住民税は次のとおり算出され、所得税と同様に、退職金などの支払いを受けるときに差し引かれます。
税額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%、道民税4%)
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金などから、税率適用後の税額から10%を控除する(90%を乗じる)措置が廃止されています。
詳しくは、平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収についてのページを参照してください。
退職所得控除額
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は、80万円) |
| 20年を超える場合 | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
(注1)勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。
(注2)障がい者になったことによって退職した場合には、上の表で算出した控除額に100万円を加算した金額が控除額となります。
(注3)平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金などから、勤続年数5年以下の役員等については、「収入金額-退職所得控除額を2分の1」とする措置が廃止されています。
※役員等とは、「法人税法第2条第15号に規定する役員」、「国会議員及び地方議会議員」、「国家公務員及び地方公務員」です。
(注4)令和4年1月1日以後に支払われるべき退職金などから、勤続年数5年以下の役員等以外についても、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します。
退職所得に係る納入方法等
退職金の支払者(特別徴収義務者)は、退職所得に係る住民税を退職金から徴収し、退職金の支払を受ける方の1月1日現在における住所地の市町村に、翌月10日までに納入することとなっています。また、納入する際には、納入書裏面の退職分離課税納入申告書(以下納入申告書)の記載も必要となります。
法人の場合
納入書裏面の納入申告書をご使用ください。
なお、納入書裏面の納入申告書には法人番号の記載が必要となります。
個人事業主の場合
納入書裏面の納入申告書には何も記載せず、別途、個人事業主用の納入申告書 [Excelファイル/15KB]に個人番号を記載し、郵送等でご提出ください。
以下の記載例をご参照ください。
納入申告書 記載例 【個人事業主の場合】 [Excelファイル/17KB]
また、個人事業主の場合は、個人番号及び身元の確認が必要となるため、下記の1又は2の書類と併せてご提出ください。
1.個人番号カード(両面)の写し
2.番号確認ができるものの写し(通知カードまたは個人番号の記載された住民票)及び身元確認ができるものの写し(運転免許証等顔写真付のもの)
留意事項
・納入書が必要な場合は、市民税課までご連絡ください。
・納入書裏面の市民税・道民税納入申告書に、特別徴収義務者の名称・所在地等を記入してください。
・徴収した税額を、徴収した月の翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌日)までに納入してください。