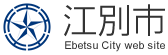令和7年度市政執行方針
はじめに
ただいま上程されました、令和7年度予算案及びこれに関する諸案件をご審議願うに当たり、私の市政に対する基本的な考えと予算の大綱についてご説明申し上げます。
多くの皆様からのご信任をいただき、私が市長に就任してから間もなく2年になろうとしております。
就任以来、市民の皆様と少人数で対話する「未来づくり懇談会」を実施してきたところであり、実施回数は11回を数えました。
私にとりまして、この懇談は、市内の各種団体の皆様と「まちづくり」や江別の「未来」を直接語り合うことができる大変貴重な場であると感じており、昨年9月からは、新たに企業版の「未来づくり懇談会」をスタートさせたところであります。
市民の皆様や企業で働く皆様との意見交換を通じて、幅広い世代の方々から、日常生活だけではなく働く立場の視点で、住環境や子育て環境、除排雪について感じていること、企業としての人材確保対策や物価高騰の影響などをお聞きすることができました。
今後におきましても、こうした対話を通して市政を身近に感じていただくとともに、江別市自治基本条例の精神でもあります協働の理念を、市民の皆様と共有しながら、「笑顔あふれるまち」「人にも企業にも選ばれるまち」を目指してまいります。
令和7年度予算への基本的な考え方
令和7年度は、「えべつ未来づくりビジョン(第7次江別市総合計画)」の2年目であります。
これまでも、経済の活性化なくして地域の発展はないとの考えのもと、将来にわたって一定の人口規模を確保するため、企業誘致による雇用確保などの市内経済の活性化に取り組んでまいりました。
こうした中、野幌若葉町の約2.7ヘクタールの市有地について、民間事業者等との連携による活用が実現したところであり、今後、子育て世帯などの定住促進や雇用の創出、さらには、新たな人の流れによる経済の好循環と地域の活性化が期待されます。
さらに、江別東インターチェンジ周辺に加えて、昨年12月、新たに江別西インターチェンジ周辺を、地域未来投資促進法に基づく重点促進区域に設定し、札幌市に隣接する優位性と高速道路の交通利便性を活かした企業誘致に弾みが付くものと考えております。
また、少子高齢化が進む中、総務省の住民基本台帳人口移動報告によりますと、当市における1年間の年少人口の転入超過数は、全国の市町村の中で、これまで6年連続で20位以内を維持してきたところであり、昨年の順位は、まだ公表されておりませんが、同様の傾向は、現在も続いているところであります。
いま、この流れを止めるわけにはいきません。
今後におきましても、子育て環境の充実や企業誘致などの取組により市内での新たな人の流れを創り出し、まちづくりの基本となる人口減少対策を、引き続き着実に進めてまいります。
さて、昨年の市政執行方針でも触れましたが、江別市の高齢化率は、令和15年に37%を超えることが見込まれております。今後も、市民の皆様が、住み慣れた地域で、安心して歳を重ね、幸せに暮らし続けられるまちづくりを進めていかなければなりません。
そのためにも、元気で健やかに毎日を送ることのできる健康寿命の延伸に向けて取り組むことが重要です。
私といたしましては、健康寿命延伸に向けて、高齢者の保健・福祉・医療施策の核になるものは、認知症への対応であると考えております。
市では、北海道情報大学や民間事業者など五者による産学官連携協定に基づき、食を中心とした認知症予防の共同研究である「江別いきいき未来スタディ」に参画しており、現在、約1,200人の市民の方にご協力をいただき、10年にわたる研究が続けられております。
また、昨年11月には、地域の公立病院と大学病院との連携により、適切な認知症治療を受けられる仕組みづくりの一環として、市立病院、札幌医科大学、江別・南空知先端医療推進協議会との間で、「認知症医療の充実に向けた包括連携協定」を締結いたしました。
今後におきましては、こうした研究や、医療の連携などにより、健康寿命延伸への不安材料でもある認知症への備えが進むことを期待しております。
さらに、同じく昨年11月には、市、北海道情報大学、江別工業団地協同組合との間で、「食と健康と情報」に関する産学官連携協定を締結いたしました。
これは全国的にも珍しい取組であり、それぞれの強みを生かして働く人の健康増進と生産性向上等を図ろうとするもので、この2月には、組合加盟企業等の従業員を対象として、生活習慣病予防セミナーを開催したところであります。
今後は、この取組をモデルとして、広く市民を対象とした事業に発展させることで、市民の健康意識の向上と健康づくりの推進に努め、「健康都市 えべつ」の実現を目指してまいりたいと考えております。
また、当市にとっての喫緊の課題は、市立病院の経営安定化であります。
コロナ禍後における医療を取り巻く環境の大きな変化により、全国的に医療機関の経営が悪化する中、市立病院においても、本年度からスタートした「江別市立病院経営強化プラン」に基づく実績が計画を大きく下回り、経営は厳しい状況となっております。
令和7年度におきましては、持続可能な医療提供体制の再構築に向けて、「経営強化プラン」の中間見直しを前倒して実施し、経営再建の取組を進めてまいります。
私は、将来の市民のためにも、長期的な視点に立って、地域医療を確保していくことが重要と考えております。
そのため、市立病院と他の医療機関等の連携強化に向けた枠組みづくりに取り組むとともに、あらゆる世代の市民が安心して住み続けられるよう、救急医療、周産期医療、高齢者医療等の地域に必要な医療提供体制の確保に努めてまいります。
ここで、令和7年度の市政を担当するに当たり、「えべつ未来づくりビジョン」の基本理念に沿って、私の基本的な考えについて申し上げます。
いつまでも元気なまち
1点目は、いつまでも元気なまち であります。
全ての市民が、生涯を通して心身ともに健康に暮らし続けるためには、保健・医療・福祉サービスの充実はもとより、生きがいや心の豊かさを育む文化・スポーツ活動を充実させるとともに、産業の振興による経済の好循環を生み出していく必要があります。
そこで、健康都市宣言に基づき、市民の皆様が、自らの健康状態を把握し、生活習慣を見直すきっかけづくりの取組を進めるとともに、文化的な活動やスポーツの振興により、「こころ」も「からだ」も健康であり続けるための環境づくりを引き続き進めてまいります。
また、経済の好循環を生み出し、地域の活性化を図るため、大都市に隣接している優位性や、4つの大学があることなどの強みを生かした企業誘致に取り組むとともに、旧江別小学校跡地の民間事業者による活用に向けた検討を進めてまいります。
さらに、一般社団法人江別青年会議所の企画による市内の高校生からの政策提言を踏まえ、高校生など若年層の視点を取り入れた企業の情報発信・認知度向上に取り組み、企業と人材のマッチングに努めてまいります。
みんなで支え合う安心なまち
2点目は、みんなで支え合う安心なまち であります。
市民の生命を守ることは、行政の使命であります。
市民の身体、生命、財産を守り、生涯にわたって住み慣れたまち「江別」で、安心して幸せに暮らし続けるためには、幅広い世代の参加による支え合いと、人と人とのつながりを大切にした協働の取組を充実させるとともに、地域防災力の向上が必要です。
そこで、防災・災害対策の拠点となる市役所本庁舎については、新庁舎建設に向けて、現在実施中の基本設計に続き、実施設計に着手し、平時には誰もが使いやすく、災害時には市民を守る安全性の高い庁舎整備を進めてまいります。
また、性別、年齢、国籍、文化の違い、障がいの有無などに関わらず、誰もが自分らしく暮らすことのできる社会を目指した「共生のまちづくり」の取組を進めるとともに、市内に在住する外国籍の方が、快適な日常生活を送ることができるよう、引き続き、日本語教育等の充実を図ってまいります。
さらに、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、安心して暮らすことができる市民生活の実現を目指し、犯罪被害者等の支援のための条例制定に向けた準備を進めてまいります。
子どもの笑顔があふれるまち
3点目は、子どもの笑顔があふれるまち であります。
江別の未来を担う子どもたちは、江別の宝です。子どもたちがいつも笑顔で、健やかに成長していくためには、安心して子どもを産み、育てられる環境を整えるとともに、子どもたちがいきいきと学べる環境づくりが必要です。
そこで、奨学金の返還支援などを通じて、引き続き、市内の保育施設で働く保育士等の確保に努めるほか、新たな放課後児童クラブの開設などにより、未就学期から学齢児童まで、保護者が安心して仕事と子育てを両立できる環境づくりを進めるとともに、小学校へのエアコン設置などにより、子どもの学習環境等の向上を図ってまいります。
また、昨年10月に設置した「こども家庭センター」による妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を引き続き行うとともに、市立病院における日帰り型と宿泊型の産後ケア事業をスタートさせることで、乳幼児の子育てに対する支援の充実を図ってまいります。
自然とともに生きるまち
4点目は、自然とともに生きるまち であります。
持続可能な社会であり続けるためには、脱炭素・循環型社会に対応することで、地球規模の環境負荷の低減に貢献し、人と自然が共に生きる環境にやさしいまちを目指す必要があります。
そこで、回収した使用済みペットボトルを原料として、再びペットボトルをつくる「水平リサイクル」の取組を、民間事業者と連携して実施するとともに、公共街路灯など公共施設の照明のLED化を進めてまいります。
また、市役所の新庁舎建設に向けて、環境負荷低減と中長期的なエネルギーコストを削減するため、ZEB化に向けた詳細について検討してまいります。
新しい時代に挑戦するまち
5点目は、新しい時代に挑戦するまち であります。
江別市が、市民の皆様にとって住みやすいまちであり続けるためには、社会や経済の変化を的確に捉え、常に、新しい分野に挑戦しなければなりません。中でも、デジタル技術の活用は、市民の利便性向上と市の業務効率化を両立させることができることから、今後の人口減少を見据え、積極的に取り入れていく必要があります。
そこで、デジタル技術の活用により、各種証明書の交付手数料の支払にコード決済をはじめとするキャッシュレス決済を選択できるようにするとともに、セミセルフレジの導入を進めてまいります。
さらに、新たにスマート農業機械の導入への補助を行うほか、スマート農業で使用する技術の他の用途への活用について、検討を進めてまいります。
また、子育て世代を中心とした道内外の方に、より江別を知ってもらうため、SNS等で発信可能な動画作成や、ラジオ番組によるPRを行うとともに、新たにまちづくりアドバイザーを設置し、シティプロモート活動を強力に推進してまいります。
予算案の大綱
次に、令和7年度の江別市予算案の大綱について申し上げます。
先般発表されました、国の令和7年度の地方財政計画では、個人所得や企業収益の増加等を踏まえ、地方全体の財政規模は、前年度と比較して3.6%の増加となり、このうち、地方交付税交付団体ベースの一般財源総額は、前年度比1.7%の増加となったところであります。
一方、地方自治体に係る歳出は、少子高齢化等による社会保障費の増加、労務単価の上昇、物価高騰などの影響で拡大傾向にあり、市の財政は、厳しい状況が続いております。
こうした状況の中、市といたしましては、財源確保と費用対効果の向上を念頭に、事業費の精査に努め、令和7年度は、「えべつ未来づくりビジョン(第7次江別市総合計画)」の2年目であることを踏まえ、まちづくり政策と未来戦略の推進に向けて、新年度予算を編成したものであります。
その結果、令和7年度の各会計予算規模と前年度当初予算との比較においては、
一般会計 587億9,000万円 11.7%の増
特別会計 265億4,400万円 3.0%の増
企業会計 187億6,751万5千円 4.1%の増
合 計 1,041億151万5千円 8.0%の増
となるものであります。
以下、令和7年度予算案の概要につきまして、第7次江別市総合計画の政策体系に基づき申し上げます。
政策1 自然・環境
第1に、「自然・環境」について申し上げます。
まず、人と自然の共生では、地域における脱炭素社会の実現に向けて、家庭用太陽光発電設備と蓄電池設置への補助を実施するほか、地域の自然環境を守るため、環境教育や緑化の推進、花のある街並みづくり活動への支援などに、引き続き取り組んでまいります。
次に、循環型社会の形成では、ごみの資源化と減量化を推進するため、自治会等が実施する資源回収事業への支援やごみの減量体験講座を通じた啓発に取り組むとともに、将来にわたって、ごみを安定的に処理できる体制を整えるため、次期最終処分場の工事に着手し、整備を進めてまいります。
政策2 産業
第2に、「産業」について申し上げます。
まず、都市近郊型農業の推進では、水利施設などの基盤整備を計画的に進めるとともに、農畜産物のブランディングや、農業者による6次産業化、新商品開発などを引き続き支援してまいります。
次に、商工業の振興では、企業ニーズを踏まえた支援策や未利用地の活用により、引き続き企業誘致を進めるとともに、就業等のために江別市に在住する外国人の日本語教育に関するニーズ調査を進めてまいります。
また、中小企業者の持続的な発展に向けて、後継者に関する経営課題に対して、事業承継の相談支援体制を創設するほか、対応する融資メニューを新設するなど、円滑な事業承継を支援してまいります。
さらに、千歳川の築堤工事に関連して、旧岡田倉庫の外構整備を進めるとともに、その付帯施設についても、かわまちづくりの拠点施設の一部として、一体的に整備を進めてまいります。
次に、観光による産業の振興では、地域おこし協力隊制度を活用し、一般社団法人えべつ観光協会が取り組む観光振興事業を引き続き支援し、観光誘客と周遊の促進に努めてまいります。
政策3 福祉・保健・医療
第3に、「福祉・保健・医療」について申し上げます。
まず、地域福祉の充実では、生活や就労に関する4つの相談窓口を1か所に集約することで、運営の効率化や窓口の連携強化を図り、利便性の向上に努めてまいります。
次に、健康づくりの推進と地域医療の安定では、骨髄ドナーに対する補助を新たに開始するほか、健康都市宣言に基づき、幅広い年代を対象とした健康教育を引き続き実施するとともに、各種イベント等において、推定野菜摂取量を測定できる機器を活用し、更なる健康保持・増進に向けた啓発に努めてまいります。
また、帯状疱疹ワクチンの定期接種化に伴い、65歳の方のほか、当面の間は、70歳以上で5歳刻みの年齢の方などを対象として接種を開始し、高齢者の疾病予防や重症化予防に努めてまいります。
さらに、市立病院については、経営安定化が喫緊の課題であることから、「江別市立病院経営強化プラン」の見直しを行うとともに、医育大学との連携による認知症医療の充実や産後ケア事業の拡充など、経営改善に向けた各種の取組を進めてまいります。
次に、障がい者や高齢者の福祉におきまして、各種計画に基づき、障がい者福祉制度や介護保険及び後期高齢者医療制度などの安定的な運営に努めてまいります。
また、医療的ケア児の保護者が、一時的な休息を確保できるよう、医療保険の上限を超える訪問看護の利用に対する助成制度を新設することにより、医療的ケア児とその保護者への支援体制の拡充を図ってまいります。
さらに、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターの運営体制を充実するとともに、 介護事業所への人材確保やICT化支援のための補助を新設することにより、 介護サービス供給体制の確保を図ってまいります。
そのほか、高齢者、障がい者、その他福祉関係団体等のバス借上げ費用への助成については、昨今の貸切バス料金高騰への対応として、1回当たりの助成上限額等を見直すことで利用の促進を図り、引き続き、高齢者等の生きがいづくりと社会参加を支援してまいります。
次に、安定した社会保障制度運営の推進では、国民健康保険事業について、医療費の増加や被保険者数の減少により、北海道に支払う一人当たりの納付金が増加しており、財源が不足することから、安定的に事業を運営するために、今般、国民健康保険税の増額改定を被保険者の皆様にお願いするものであります。
また、特定健康診査の受診率や、特定保健指導の利用率の向上に向けて、データヘルス計画に基づいた保健事業を、引き続き推進してまいります。
政策4 安全・安心
第4に、「安全・安心」について申し上げます。
まず、地域防災力の向上では、自然災害等における情報発信のため、インターネット回線を利用した防災行政無線を新たに導入するとともに、災害対応物品の整備を計画的に進めてまいります。
また、耐震化が必要な市役所本庁舎については、国の起債制度の期限等も考慮しながら、建設に係る基本設計を完了させるとともに、早期建設に向けて実施設計を進めてまいります。
次に、消防・救急の充実では、本年10月から消防通信指令の共同運用を開始することにより緊急時における対応力を強化するほか、大麻出張所に女性専用のシャワー室や仮眠室を整備することにより、女性消防職員の勤務環境改善に努めてまいります。
政策5 都市生活
第5に、「都市生活」について申し上げます。
まず、市街地整備の推進では、市営住宅について、子育て世帯が住みやすい住環境や、多様な世代のコミュニティが形成される団地を目指し、あけぼの団地再整備計画の策定を進めてまいります。
また、駅周辺を拠点とするコンパクトで機能的なまちづくりを基本として、既存の都市機能や周辺環境に配慮した計画的な土地利用の検討を引き続き進めるとともに、周辺環境と調和した安全で快適な公園整備を進めてまいります。
さらに、上下水道においては、災害に強く、安全で安心して使える水道水を安定的に供給するため、配水池の増設工事のほか、老朽配水管の更新や耐震化を進めるとともに、衛生的な生活環境を確保するため、下水道管路の更新や処理場・ポンプ場の設備更新などを計画的に進めてまいります。
次に、暮らしを支える交通環境の充実では、宅地造成による交通量の増加に対応するため、「元江別中央通り」や「兵村4丁目通り」などの幹線道路の整備を進めるほか、老朽化した生活道路や橋梁などの改修により、安全で快適な道路環境の整備を進めてまいります。
また、冬の市民生活に不可欠な雪対策について、除雪機械の更新等を計画的に進めるほか、作業員の人員確保に向けた資格取得を支援するなど、安定的な除排雪体制の確保に努めてまいります。
次に、暮らしを豊かにする技術の活用では、住民記録をはじめとした基幹系システムの標準化を計画的に進め、本年11月の新システムの運用開始に向けて、整備を進めてまいります。
政策6 子育て・教育
第6に、「子育て・教育」について申し上げます。
まず、子育て環境の充実では、乳幼児の健全な発達の確認や、保護者の育児相談に早期から応じるため、1か月児健診の受診費用への支援を開始するほか、地域全体で子どもたちを見守る環境の充実を図るため、子ども食堂等を運営する団体の活動への補助を、新たに実施してまいります。
また、保育の待機児童解消のため、民間保育施設等の整備に対して支援するとともに、障がい児を受け入れる保育施設の人員体制強化に対して新たに支援することで、保育環境の充実に努めてまいります。
さらに、子育て世帯の転入や共働き世帯の増加を踏まえ、3か所の放課後児童クラブを新たに整備し、令和8年度からの受入態勢の整備を進めてまいります。
次に、子どもの教育の充実では、引き続き情報活用能力の系統的な育成を図り、確かな学力を支える資質・能力を高めていくため、小中学校に導入した児童生徒用タブレット端末や指導者用端末について、計画的に更新を進めてまいります。
また、全ての中学校で実施している放課後学習について、学習サポート教員の派遣回数を拡大するなど、児童生徒一人ひとりの理解度に応じたきめ細かな指導を行うことで、教育内容の更なる充実を図ってまいります。
さらに、中学校3校に導入している部活動指導員について、他校への拡充を図るほか、大学と連携し、将来的な部活動の拠点づくりを見据えた実証事業を行うなど、引き続き、学校や関係団体の意見を聴きながら、部活動の地域展開等に向けた検討を進めてまいります。
政策7 生涯学習・文化・スポーツ
第7に、「生涯学習・文化・スポーツ」について申し上げます。
まず、生涯学習の充実では、情報図書館において、閲覧用雑誌の導入を支援する企業等を新たに募集し、雑誌カバー等を活用した広告による財源確保を図り、図書館資料の充実に努めてまいります。
次に、ふるさと愛の醸成と地域文化の継承では、セラミックアートセンターにおいて、独創的な技法で世界的にも著名な陶芸家である尾形香三夫(おがた かみお)氏の企画展を開催するなど、やきもの文化の発信に取り組んでまいります。
また、地域の専門的な指導者の協力により実施している「土曜広場」について、通学している学校で実施される講座に限らず、全ての会場の中から講座を選択できる枠組みとして実施することで、子どもの文化に親しむ機会の充実を図ってまいります。
次に、市民スポーツ活動の充実では、子どもから大人まで、幅広いスポーツ活動を引き続き支援するほか、道内プロスポーツチーム等と連携し、子どもたちとトップアスリートとの交流機会を提供するなど、スポーツの振興に努めてまいります。
政策8 協働・共生
第8に、「協働・共生」について申し上げます。
まず、協働のまちづくりの推進では、市民が主体となった協働の取組を引き続き支援するとともに、市民、自治会、市民活動団体、企業、大学などの各種団体と連携して魅力ある協働のまちづくりを推進してまいります。
また、まちづくりのパートナーとして重要な役割を担っている自治会について、担い手不足などの課題解決に向けたワークショップを江別・野幌・大麻の3地区で実施することにより、若い世代の自治会活動への参加を促進してまいります。
さらに、貴重な知的資源であり、人材育成の場でもある市内4大学について、市と大学が連携して研究や地域活動に取り組む各種事業を引き続き推進してまいります。
政策9 計画推進
第9に、これまでの8つの政策を支える「計画推進」について申し上げます。
まず、市政運営に関して、効率的な行政サービスの執行と財政の健全性確保に引き続き努めるとともに、企業版を含めたふるさと納税の拡大に向けた取組を進めてまいります。
次に、情報発信に関して、シティプロモーションを強化するため、新たに、江別市の魅力を発信するための動画やラジオなどによる情報発信を通じて、まちの魅力の効果的な発信に努めてまいります。
以上が歳出予算の概要でありますが、次に、歳入の見通しの主なものにつきまして、ご説明申し上げます。
まず、市税につきましては、国による定額減税終了の影響による市民税の増加や、地価上昇や資材価格高騰などの影響による固定資産税の増加などから、市税全体では前年度当初に比べ、5.8%増の133億8,300万円を見込んでおります。
また、地方交付税は、4.3%増の128億1,000万円、地方消費税交付金は、1.6%増の31億3,000万円を見込んでおります。
その結果、一般財源総額では、302億7,330万円となり、前年度より2.7%の増となったところであり、今後とも、市税等の自主財源の確保に努めてまいります。
次に、市債の発行につきましては、環境クリーンセンター基幹的設備改良事業のほか、道路整備などの財源に充てるため、総額では、45億5,190万円となりました。
市債については、今後とも将来世代と現役世代との負担割合などに十分配慮しつつ、投資的事業の重点化や平準化などにより、計画的な発行に努めてまいります。
その他、予算案の詳細につきましては、「令和7年度各会計予算及び予算説明書」などをご参照いただきたいと存じます。
以上、令和7年度予算案の大綱について申し上げました。
私は、昨年の市政執行方針の中で、「これからの10年、またその先の10年と、未来は必ずやってくる。」と申し上げました。
20年、30年先、誰もが幸せをつかむことができる未来をつくり、子どもたちの世代に、まちづくりのバトンをつなぐことが、私たちの世代の務めであります。
そのためにも、子育て世代から住みよいまちとして選ばれ、さらには、江別に住む子どもたちが、大人になったときに、幸せな未来が待っていると、大人も子どもも感じることのできるまちに育てていく必要があります。
昨年11月、「子どもが主役のまち宣言」をいたしました。
その冒頭で、「未来を担う子どもたちは、江別の宝です。すべての子どもたちが、いつも幸せを感じ、未来への夢や目標を抱くことができるまちづくりは、江別市民すべての願いです。」としているとおり、「すべての子どもたちが主役」のまちづくりが必要です。
市の子ども関連施策は、今後、この宣言の内容を踏まえて実施していくとともに、この宣言にある「子どもの幸せを第一に、子どもにとって最も良いことを考える」まちを実現するため、子どもの権利条例の制定に向けた準備を進めてまいります。
また、冒頭にも申し上げました市立病院については、市内唯一の公立病院として、将来にわたって地域に必要な医療を確保するという使命を果たすことができるよう、病院事業管理者とともに、引き続き全力で医師確保に努めるほか、病院職員全体で「断らない医療」を実践するなど、経営再建に向けた取組を進めてまいります。
結び
結びになりますが、「えべつ未来づくりビジョン(第7次江別市総合計画)」の将来都市像は、「幸せが未来へつづくまち えべつ」であります。総合計画の下で、これからも「江別市に住んで良かった」、「このまちにずっと住み続けたい」と思っていただけるよう、一歩一歩、着実にまちづくりの歩みを進めてまいります。
市民の皆様並びに議員各位の特段のご理解とご協力をお願い申し上げ、令和7年度の市政執行方針並びに各会計予算案の説明とさせていただきます。