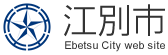事業者の皆さん、ご存じですか?~知っておきたい制度や仕組み~
はじめに
雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保を図ることなどを目的とした法律「男女雇用機会均等法」は昭和60年に制定されました。制定以降、社会情勢と合致するよう様々な見直しが行われています。
ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組んでみませんか?
固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、「営業職に女性はほとんどいない 」、「課長以上の管理職は男性が大半を占めている」等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組をいいます。
【厚生労働省】女性活躍推進のための取り組み「ポジティブ・アクション」を進めましょう(リーフレット) [PDFファイル/831KB]
あなたの職場には「一般事業主行動計画」がありますか?
共働きが多い、現代。性別や子育ての有無に関わらず、誰もが働きやすい職場環境づくりがより重要となります。
「一般事業主行動計画」とは、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間 、(2)目標 、(3)目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定するものです。
雇用する従業員が101人以上の企業は、北海道の労働局へ届けることが義務付けられており、100人以下の起業は努力義務となっています。
「ハラスメント対策」は、できていますか?
●セクシャルハラスメント(職場や求職者等)
●パワーハラスメント
●妊娠・出産など、育児・介護休業等に関するハラスメント
●カスタマーハラスメント
これらのハラスメントについて、事業主は防止措置を行うことが義務となっています。
ワーク・ライフ・バランスが図られた職場となっていますか?
「男性は職場、女性は家事・育児」と言われてきたこの国では、職場における男性の長時間労働や女性の家庭での仕事の片寄りの名残があります。しかし、現在は共働きが主流であり、男性も女性も職場・家庭での仕事を共に担っていくことが男女共同参画において、重要なことです。「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」は、個人の生活、企業の経営戦略、社会全体の活力の面で、相乗効果を生み出します。人ひとりが、それぞれの希望に応じて「仕事(ワーク)」と「家庭生活や地域活動等の私生活(ライフ)」の調和を図り、その両方を充実させる状態のことです。実現に向けて取り組むことで、企業は、従業員の意欲、能力、創造性を引き出して生産性の向上を図れるとともに、優秀な人材の確保・定着が可能になるほか、少子化の抑制、労働人口の確保など、社会全体の活性化にもつながります。
【内閣府HP】カエルジャパン・仕事と生活の調和推進
●労働時間等を見直してみませんか?
労働時間等の見直しガイドラインがあります。
●働き方・休み方について改善したいけれども、どうすればいいか…
北海道労働局には、働き方・休み方改善コンサルタントがいます。
→【厚生労働省】労働時間等の設定の改善 や 事例集や支援策のハンドブックの掲載もある 働き方改革について をご確認ください。
●職場で働くだけが、仕事ではありません。
コロナ禍以降、働き方の多様性の考え方が広まり、テレワークという手法もあります。
育児や介護をしながら働きやすい職場づくり、進めていますか?
- 【厚生労働省】仕事と育児/仕事と介護の両立支援ガイド [PDFファイル/2.66MB]
- 【厚生労働省】「育休復帰支援プラン」策定マニュアル [PDFファイル/77.95MB]
- 仕事と介護の両立支援に関するガイドやマニュアル
→厚生労働省のHPをご確認ください。
- 【厚生労働省】仕事と家庭の両立支援プランナーによる支援
- 【両立支援等助成金】仕事と家庭生活を両立するための環境整備に取り組んだ事業主への助成金
→厚生労働省のHPをご確認ください。
「イクメン」から「共育(ともいく)」の時代へ
男性労働者が育児をより積極的に行うことや育児休業を気兼ねなく取得できる環境づくりのテーマとして「イクメン」が広まりました。
共働きが多い現代。男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「共に育てる」に取り組める社会を目指す後継プロジェクト【厚生労働省】「共育(ともいく)プロジェクト」(令和7年7月)がスタートしました。
育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように「産後パパ育休」、「パパ・ママ育休プラス」等の制度があります。これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
各種支援策や制度、ご存知ですか?
- 最低賃金・賃金引き上げに向け、国などが実施する各種支援策があります。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
- 再就職、転職、スキルアップを支援する「求職者支援制度」があります。
【「求職者支援制度」って?】
・再就職や転職を目指す求職者の方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。
・訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。
・離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。
・給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。
詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。
経済社会の活力の維持のため~少子高齢化が進む現代の雇用のあり方~
人生100年時代を迎えている現代。 働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮・活躍できる環境の整備を目的とし、「高年齢者雇用安定法」が令和3年4月1日に改正されました。
65歳までの雇用確保(義務) + 70歳までの就業確保(努力義務)
対象事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
対象となる措置
次の(1)~(5)のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を行うよう努める必要があります。
(1)70歳までの定年引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳までに以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業