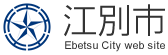大学連携 調査研究事業(令和6年度)
令和6年度 江別市大学連携調査研究事業 補助金採択事業
今年度は13件の応募があり、選考の結果以下の7事業を採択しました。
採択事業については、江別市の所管課と連携しながら事業を推進していただくとともに、研究結果を地域課題の解決や施策へ活用することについて検討していきます。
※採択事業は、大学順に掲載しています。
1.Ebetsu型部活動地域移行モデルの構築 北翔大学 永谷 稔 教授 566,000円
本研究は、令和5年度から7年度までにおける休日の部活動の段階的な地域移行について、江別市内の中学校(中学生)を対象に活動機会提供と本学学生の指導機会を醸成し、Ebetsu型部活動地域移行モデル構築を検討する3年次計画の2年目に当たるものである。計画に従い2年目は、複数クラブ・競技対応、実施回数の検討を進めるものであるが、指導者不足校への学生指導者派遣、支援組織体制づくりを含め、双方の満足度向上と将来に渡るモデル継続性を高められるよう成果を出したい。
2.江別市における社会資源を活用した不登校支援に関する調査 北翔大学 澤 聡一 准教授 420,000円
近年増加している不登校に対し,学校内外で様々な支援が行われているが,支援を利用しない家庭も増加している。本研究では,不登校当事者・家庭が求める地域の社会資源の実態を明らかにするとともに,それらの社会資源と学校が効果的に連携する支援のあり方について調査する。調査は,江別市内外の不登校支援団体のほか,福祉施設等にも協力を求め,他地域との比較を行う定量的調査と,当事者,支援者への聞き取りによる定性的調査の両面から行い,これらを通して,江別市に必要な支援の提言を行うことを目的とする。
3.小学生の通学時におけるかばんの重さと心身の健康状態との関連 北翔大学 野口 直美 准教授 180,000円
本研究では、小学生の通学時におけるかばん(携行品を含む)の重さに対する認識と心身の健康状態について調査研究を行うものである。具体的には、江別市内の小学生とその保護者を対象に通学時のかばんの重さや心身の健康状態について調査を行う。そして、これらの関連について明らかにし、子どものウェルビーイングの向上を目指した通学時のかばんの在り方について提案することを目的とする。
4.飼い主がもつ車中泊避難への意識調査 酪農学園大学 中村 達朗 講師 360,000円
災害時における車中泊避難は健康被害の懸念から推奨されていないが、ペットを飼育する家庭ではそれを選択する可能性が高い。飼い主は災害時に車中泊避難を選択するか否か、また、避難場所や避難生活に必要な準備や心得はもっているかを事前に把握することは、公的な防災対策を講じる上では重要な情報である。本調査研究は、飼い主の車中泊避難への意識調査を行い、本学および江別市が災害時に備えて準備すべき課題を明らかにするための情報収集を目的とする。
5.野菜摂取促進につながる市民の認識とヘルスリテラシーの分析 酪農学園大学 木村 宣哉 講師 234,000円
今年度、当研究室では江別市健康福祉部健康推進室と連携し、市内のスーパーマーケットや各種イベントなどで江別市民の野菜摂取の意識啓発を行う予定である。そこで、イベントに参加した市民を対象に、野菜摂取量の測定および野菜摂取に関する認識やヘルスリテラシーの調査を行い、市民の野菜摂取につながる要因を分析する。
6.江別市内における経済波及効果推計ツールの開発 北海道情報大学 藤本 直樹 教授 88,400円
令和6年4月より,「幸せが未来へつづくまち・えべつ」を将来都市像とする江別市第7次総合計画がスタートした。江別市は,拡大する札幌都市圏の受け皿として発展を遂げてきたが,今後は,少子高齢化に対応した都市基盤や交通体系の再編など,新たな課題が生じてきている。
一方,コロナ禍や過度の円安を発端とする物価高騰で,市内各産業が疲弊し,一部市民の生活が困窮している。これらに対応するため,江別市では「物価高騰対策関連事業」として,住宅リフォーム補助金,えべつギフト事業,プレミアム商品券事業などを推進してきた。
本研究のねらいは,物価高騰対策関連事業に焦点を当て,産業連関分析によって江別市内への経済波及効果を推計するものである。本研究での分析項目は,いわゆる経済波及効果(直接効果,一次・二次波及効果)に加えて,江別市内での付加価値額の増加(雇用者所得増加額,営業余剰増加額,税収増加額)や雇用機会の創出効果(人数)を産業別に推計することである。
産業連関分析は,北海道新幹線の開業やYOSAKOIソーラン祭りの開催など,ハード整備やソフト施策を問わず,経済波及効果の推計に最もよく用いられる手法である。本研究の目的は,江別市の産業連関表を作成し,地域経済の強みや弱みを分析するとともに,市職員が今後の事業や施策の評価でも容易に活用できる推計ツールを開発することである。
7.「新しい健康社会」の実現に向けた江別市民の健康活動とその行動変容ステージに関する実態調査 北海道情報大学 本間 直幸 教授 351,600円
本邦では2024年から健康日本21(第三次)がスタートし、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンとして掲げ、「誰1人取り残さない健康づくり(Inclusion)」と「より実効性をもつ取組の推進(Implementation)」に重点を置き、国民の健康づくりを社会全体で、総合的・計画的に推進するものとしている。その基本的な方向の1つとして「個人の行動と健康状態の改善」があげられている。本調査研究では、江別市の高齢者を中心に働く世代を含めた男女に対し個人レベルでの健康への取組み(健康行動)の現状を調査することで、健康行動に関し、地域住民が現在どのような変容ステージにいるか、その特徴を明らかにする。また、現在のステージから1つでも先に進むために、どのような働きかけを必要としているかを明確にすることで、地域社会が推進すべき行動変容支援のあり方等について提言を行う。
募集期間
3月29日(金曜日)~5月17日(金曜日) 応募事業13件 補助金申請総額 5,645,581円
採択事業7件 補助金交付金額 2,200,000円
採択事業の選考方法
応募のあった事業については、庁内で評価選考を行い採択を決定。選考決定の方法は次の(a)と(b)による。
(a)各事業の評価採点
調査研究のテーマを所管する部において、次の(ア)から(オ)までの採点項目を5段階で評価し採点。
| 採点項目 | 説明 |
|---|---|
| (ア)課題認識 | 現在の市の政策課題、市民ニーズに合ったものか。 |
|
(イ)創造性・独創性 |
新たな視点、着眼点に基づくものか。今まで江別で行われていない試み、または今までの試みを展開するものであるか。 |
| (ウ)具体性 | 市政課題の対応、地域活性化の実現のための具体的な手法が示されているか。 |
| (エ)実現性 | 市民や地域の課題等に活用できる実現可能性の高いものか。実現のための手法等は適切か。 |
| (オ)効果 | 活動による市民や地域への広がり、影響性があるか。 |
(b)庁内選考会
(a)による評価採点をもとに、庁内選考会で協議の上、決定。